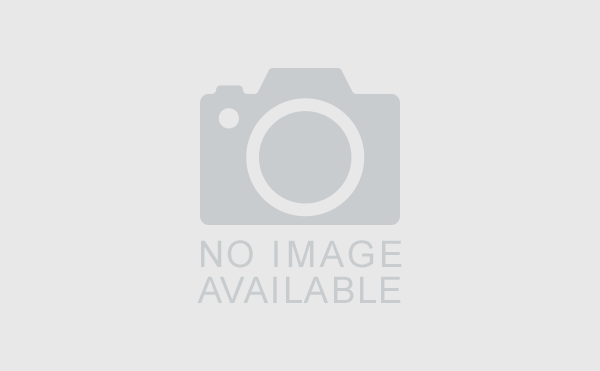インベンションをやさしく解説する。第2回 新たな切込み
2025年7月19日(土)午後2時開演
足立サロン 限定30人 要予約
大阪市西淀川区御幣島1丁目5ー6
この日のレッスン生徒(公開・非公開いずれも)募集しています
入場料:3,000円・
お申し込み・お問合わせは080-3038-8671
https://m-ohtake.classic-market.jp/contact/
第1部・コンサート
ドビュッシー:ベルガマスク組曲他
第2部・講座
インベンションをやさしく解説する。新しい切込み
第1番・第3番・第4番・第8番
新たな考え方で「大切なもの」を抽出する。
今まであまりされていなかった方法で、インベンションに切り込んでみます。もちろんそれによって「演奏」「音楽理解」あるいは「作曲・創作」などのヒントになりえることでなければいけません。
私は「インベンションは合奏曲」として考えています。登場人物が2人、3人で、それぞれが主張しあい、音楽を展開させていく。そうすると「自分の頭の中に2人3人と演奏者」を作っておかないといけない。
かつての音楽家たちが「鍵盤楽器」に託したこと、それは「一人で合奏をする」ということだと考えています。私はこの点を「インベンションの前書き」にバッハが書かなかったことに対し、非常に遺憾に思っています。
インベンションは、ヨハン・セバスチャン・バッハが自分の息子たちを、一人前の音楽家にするために作曲されました。パパ・バッハも、人の子です。ある息子には手をかけすぎて「息子の宿題」まで代わりにやってやったり、ある息子には、ほっぽらかしだったり、できの悪い息子には、異常に心配したり、といろいろだったようです。ですので、バッハの息子たちは、それぞれ違うタイプの音楽家になり、中には次の時代の音楽に影響を与えた人もいました。
さて、インベンションの解説書を見ると、たくさんの言葉が並んでいます。でもなるべく「専門用語を極力減らして」解説してみたいと思います。また、やむを得ず出てきた専門用語を「わかりやすく言い換えたり」してみたいと思います。バッハの名手、グレン・グールドが「じゃあフーガを書いてみよう」で言ったように・・・
.png)